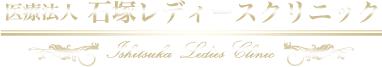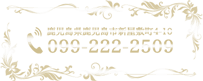厚生労働省の定める院内掲示事項
当院は、以下の指定医療機関になります
- 厚生労働省が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関
- 生活保護法指定医療機関
入院基本料に関する事項
- 有床診療所入院基本料1
当診療所には、10名以上の看護職員《助産師・看護師および准看護師》が勤務しております。
九州厚生局への届出事項
当診療所には以下の施設基準に適合している旨の届け出を行っております。
- 明細書発行体制等加算
- 夜間・早朝等加算
- 時間外対応加算1
- 外来感染症対策向上加算
- 医療情報取得加算
- 医療DX推進体制整備加算
- 外来後発医薬品使用体制加算
- がん治療連携指導料
- HPV核酸同定検査
- 婦人科特定疾患治療管理料
- 一般不妊治療管理料
- 有床診療所入院基本料1
- ハイリスク妊娠管理加算
- 外来ベースアップ評価料(I)入院ベースアップ評価料
常時夜間緊急体制が確保され、入院患者様の緊急時にはすぐに対応しております
- 夜間担当医師
石井裕子 山元志奈子
当診療所は屋内全面禁煙です
当診療所では個室入院の際には差額室料を頂いております
| 特室 | 12,000円 |
| 個室(シャワー付き) | 6,000円 |
| 個室(シャワー無し) | 5,000円 |
当診療所では以下の項目に対して実費負担をお願いしております
| 薬剤容器代 | 小50円 大70円 |
| 診断書・証明書料金 | 550〜5,500円 |
明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。
明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合その代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にその旨お申し出ください。
夜間・早朝等加算
土曜日12時~13時の間に受診されますと夜間・早朝加算が算定されます。
時間外対応加算1
当院では、継続的に受診している患者様からの電話等によるお問い合わせに対し、原則として当院にて、常時対応できる体制を取っております。
夜間・休日などの緊急時においては、(Tel 099-222-2509)までご連絡をお願いいたします。
医療情報取得加算
オンラインで資格確認や受信歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
医療DX推進体制整備加算
- オンライン請求を行っております。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等において、閲覧又は活用できる体制を有しております。
- 電子処方箋の発行体制や電子カルテ情報共有サービスの取り組みを実施してまいります。今後導入予定です。
外来感染対策向上加算
当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。
- 感染管理者である院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。
- 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に研修会を年2回実施します。
- 感染性の高い疾患(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と動線を分けた診療スペースを確保して対応します。
- 抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。
- 標準的感染予防策を踏まえた院内感染マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進して行きます。
- 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け院内感染対策の向上に努めます。
外来後発医薬品使用体制加算について
当院は、後発医薬品の使用促進を図るとともに医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
医薬品の供給不足が発生した場合に医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。
変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、当院職員までご相談ください。
生活習慣病管理料(II)
高血圧症、脂質異常、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者さまが対象です。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期投与を行うことは対応可能です。
がん治療連携指導料
計画策定病院と連携をとりながら治療を行います。
長期収載品の処方に係る選定療養について
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。
選定療養は保険給付ではない為、公費も適用になりません。
適正な意思決定支援に関する指針
下記の通り「適切な意思決定支援に関する指針」を策定いたしました。
- 基本方針
人生の最終段階を迎える患者がその人らしい最期を迎えられるよう、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族、親権者に対し適切な説明と話し合いを行い、各々の意思が尊重されるよう医療・ケアを進めます。 - 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援
- 2-1 患者本人の意思が確認できる場合
患者本人による意思決定を基本とし、家族等も関与しながら、医療・ケアチームも協力し、方針を決定する。決定内容は都度カルテに記載する。
時間の経過、医学的評価の変更、環境の変化に伴い意思は変化するので患者はいつでもその意思を伝えることができるように支援する。 - 2-2 患者本人の意思が確認できない場合
患者本人の意思を推定できる場合には、それを尊重し患者にとって最善の医療・ケアの方針を慎重に検討し決定する。推定も困難な場合は家族・チームで最善の医療・ケアの方針を慎重に検討し決定する。
- 2-1 患者本人の意思が確認できる場合
- 意思決定困難者の意思決定支援
障害や認知症などで決定困難な場合はできる限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を家族および関係者、医療・ケアチームが関与して支援する。 - 身寄りのない方の意思決定支援
下記の通り「身体的拘束を最小化する取り組み」を策定いたしました。- 1. 石塚レディースクリニックでは「患者または他の患者等の生命・身体を保護するために緊急時やむを得ない」場合を除き身体的拘束を行いません。
- 2. やむを得ず身体拘束を行う場合にはその「態様」「時間」「患者の心身の状況」「緊急やむを得ない理由」を記録します。
- 3. 身体的拘束最小化対策にかかる医師として院長が、看護職員として看護主任が中心となりチーム結成し以下を遂行します。
- 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する
- 「身体的拘束を最小化するための指針」を作成し、職員に周知し活用する
- 定期的に指針の見直しを行う
- 入院患者にかかわる職員を対象として「身体的拘束を最小化する研修」を定期的に行う